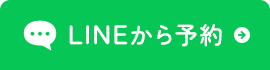注意すべき感染症について
百日咳
 百日咳は、百日咳菌が原因となり、顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性にせき込み(スタッカートと呼ばれます)、最後にヒューという呼吸をするのがけいれんのような強い咳が特徴の呼吸器感染症です。名前の通り咳が何週間100日近くにもわたって続き、生後6ヶ月未満の乳児がかかると、重篤な症状を引き起こすことがあります。症状が進むと、咳の発作によって息が苦しくなったり、顔色が悪くなったりすることもあります。大人が感染すると、激しいせき込みによって肋骨を骨折することがあります。百日咳は生後2か月からの定期ワクチンを接種することで予防できますが、百日咳は、百日咳菌という細菌によって引き起こされ、ワクチンで予防できる感染症です。しかし、ワクチンの効果は時間とともに弱くなるため、現在でも周期的な流行が見られます。学童期や大人が感染源となるケースも増えています。小さな赤ちゃんを守るためにも、周囲の大人やご兄弟のワクチン接種も重要です。
百日咳は、百日咳菌が原因となり、顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性にせき込み(スタッカートと呼ばれます)、最後にヒューという呼吸をするのがけいれんのような強い咳が特徴の呼吸器感染症です。名前の通り咳が何週間100日近くにもわたって続き、生後6ヶ月未満の乳児がかかると、重篤な症状を引き起こすことがあります。症状が進むと、咳の発作によって息が苦しくなったり、顔色が悪くなったりすることもあります。大人が感染すると、激しいせき込みによって肋骨を骨折することがあります。百日咳は生後2か月からの定期ワクチンを接種することで予防できますが、百日咳は、百日咳菌という細菌によって引き起こされ、ワクチンで予防できる感染症です。しかし、ワクチンの効果は時間とともに弱くなるため、現在でも周期的な流行が見られます。学童期や大人が感染源となるケースも増えています。小さな赤ちゃんを守るためにも、周囲の大人やご兄弟のワクチン接種も重要です。
咳が長引く、特に夜間の発作がつらそう、ゼーゼーとした咳が続いているなどの症状がある場合は、できるだけ早く受診してください。
2025年の百日咳の大流行を踏まえて、乳児期の定期ワクチン接種に加えて、就学前6歳時でのDPTワクチンの追加接種が推奨されております。またtDAPワクチンという海外製のワクチンは10歳以上から接種可能であり、国内で使用されるtDPTワクチンより接種による腫れなどが少なく効果的であることが報告されています。
tDAPワクチン接種を検討する方は、お気軽にご相談ください。
突発性発疹
突発性発疹は、主に1歳前後の乳児がかかるウイルス性の疾患で、ヒトヘルペスウイルス6型または7型が原因です。突然39℃を超える高熱が出るのが特徴で、3〜4日間続いたのち、熱が下がると全身に赤い鮮やかな発疹が出現します。発疹はかゆみなどなく数日で跡を残さずに自然に消えていきます。2歳前後で突発性発疹に罹患すると解熱後の発疹がなく、診断に苦慮することがあります。発熱中は比較的機嫌がよく見えることが多い一方、解熱後に発疹が出現するタイミングで非常に不機嫌になったり、食欲が落ちたりすることがあります。症状が出た際は、突発性発疹の可能性も含めて医療機関での診断を受けると安心です。発疹が出現しても、突発性発疹か不安な場合には、受診していただく方が良いでしょう。
伝染性紅斑(リンゴ病)
伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19の感染によって発症するウイルス性疾患です。いわゆる「りんご病」とも呼ばれ、頬が赤くなる独特の紅斑が特徴です。2週間ほどの潜伏期間を経て、顔に紅斑が現れ、その後、腕や脚など四肢へと広がっていきます。
発熱はあまり見られず、症状が軽いため気づかれにくいこともあります。紅斑が出た段階ではすでに感染力はなくなっており、学校や保育園の登園制限はありません。ただし、免疫の低下した状態である妊婦さんや血液の基礎疾患を有する一部の人にとっては注意が必要なウイルスですので、接触には配慮が必要です。リンゴ病と思ったら、人ごみに行くのは避けた方が良いでしょう。
溶連菌感染症(ようれんきん)
溶連菌という細菌による感染症で、高熱やのどの強い痛み、扁桃腺の腫れ、舌が赤くなる「いちご舌」などが見られます。抗菌薬による治療が必要なため、症状がある場合は医療機関を受診しましょう。
アデノウイルス(プール熱)
発熱、のどの痛み、結膜炎(目の充血や涙)、下痢など、さまざまな症状が出るウイルス感染症です。38度以上の高熱が続くこともあり、感染力が強いため注意が必要です。