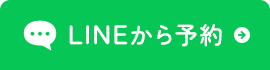子どもの慢性外来
 当院では、夜尿症、頭痛、便秘、ヘルニアなど慢性の経過を有する疾患をお持ちのお子さまに専門性の高い治療を行い、丁寧な経過観察を行っています。
当院では、夜尿症、頭痛、便秘、ヘルニアなど慢性の経過を有する疾患をお持ちのお子さまに専門性の高い治療を行い、丁寧な経過観察を行っています。
慢性疾患をお持ちのお子様だけでなく、ご家族の負担や悩みに丁寧に耳を傾け、困りごとに寄り添いながら継続的なサポートを行っています。
夜尿症(おねしょ)
夜尿症とは
 おねしょ(夜尿)やおもらし(尿失禁)は、ほとんどのお子様が成長とともに改善していきます。しかし、その改善には個人差が大きくあります。
おねしょ(夜尿)やおもらし(尿失禁)は、ほとんどのお子様が成長とともに改善していきます。しかし、その改善には個人差が大きくあります。
5歳を過ぎても月1回以上のペースでおねしょが3ヶ月以上続く場合、「夜尿症」と診断します。膀胱の発達の遅れや、睡眠中の排尿をコントロールする機能が未熟であることが主な原因とされています。
5歳の段階で6-7人に1人、10歳の段階で20人に1人、15歳の段階では100人に1人の割合でみられる比較的よくみられる症状です。
また遺伝的な要因が関与しており、両親のどちらかが小児期に夜尿症であった場合にはお子さまにも同じ傾向が見られることがあります。
おねしょが長く続くことで、お子様の自尊心や羞恥心に影響が出ている場合や、ご家族が洗濯や片付けの負担でストレスを強く感じ、「少しでも早く治したい」とお考えのときには、一度ご受診のうえ、ご相談ください。また、学校の宿泊行事などで本人にプレッシャーを感じやすいこともあり、早めの対応が安心につながることがあります。
夜尿症の原因
夜尿症は育て方や性格によって生じるものではありません。叱ったり、無理やり夜中に起こすことは、改善の妨げになることがあります。
夜尿は、就寝中に作られる尿量や膀胱の容量が深く関係しています。また夜尿症のあるお子さまは眠りが深いことが多く、尿意で目覚めにくい傾向があります。
ただし、日中におもらし(尿失禁)が見られる場合や便の失禁などがみられる場合には、別の原因が隠れていることも考えられますので、早めの受診をおすすめします 。
頭痛
 子供の頭痛は一時性頭痛といわれる片頭痛、緊張性頭痛(慢性連続性頭痛)と二次性頭痛と言われる原因として別の病気がある頭痛に分けられます。
子供の頭痛は一時性頭痛といわれる片頭痛、緊張性頭痛(慢性連続性頭痛)と二次性頭痛と言われる原因として別の病気がある頭痛に分けられます。
二次性頭痛には、インフルエンザや溶連菌などの感染症、急性副鼻腔炎などから髄膜炎や脳腫瘍、てんかんといったものまで原因は多岐にわたります。特徴として激しい頭痛、頭痛の頻度が増していく、鎮痛剤を内服して痛みが再発する、発熱や咽頭痛などを伴う、歩行のふらつきや嘔吐があるなど見られ、早めの受診をしていただくことが大切です。
一方、一時性頭痛は大きく片頭痛と緊張性頭痛(慢性連日性頭痛)に分けられます。
10歳前後を境に、10歳までは片頭痛が多く、10歳以上になると緊張性頭痛へと移行もしくは発症することが多いとされています。片頭痛は強い痛みが特徴ですが、寝れば治ることが多く、遺伝性が指摘されています。10歳以降に見られる緊張性頭痛(慢性連日性頭痛)は痛みは強くないものの、数日にわたって続くことが多く、平日の朝の頭痛は学校欠席につながりやすいのも特徴です。ストレスや疲労、スマホ画面の長時間使用なども悪化要因となり近年、増加しています。学校欠席は学業の低下につながり、家族の心配が非常に強くなります。しかし、過剰な心配や原因探しが頭痛の悪化につながることもあり、本人だけでなく、見守る家族の負担が大きくなることもしばしばあります。また女児における生理関連の頭痛に関しては、薬剤が効きにくいことがあり、この場合には年齢によって産婦人科との連携が必要となることがあります。
当クリニックでは、どのタイプの頭痛であるのか、他の病気が隠れていないかなどを確認しながら、本人と保護者の方のお話しをよく伺い、適切な治療法を探すことをゴールにしています。またお子様本人、またご家族の方に寄り添いながら、成長を待ち、乗り越えていくことをサポートしていく姿勢をとっております。場合によっては、専門施設と連携していくこともありますので、お困りのことがありましたら、ご相談ください。
こどもの便秘
 子供の10人に1人は便秘というデータもあるように、便秘は比較的よく見かける疾患です。慢性便秘診療ガイドラインでは、本来、排出すべき糞便が十分量かつ適切に排出されない状態を便秘と定義しています。目安としては週に2-3回以下、もしくは5日以上排便がない、毎日出ていても排便時の痛みや、肛門が切れるという場合には便秘と言えます。
子供の10人に1人は便秘というデータもあるように、便秘は比較的よく見かける疾患です。慢性便秘診療ガイドラインでは、本来、排出すべき糞便が十分量かつ適切に排出されない状態を便秘と定義しています。目安としては週に2-3回以下、もしくは5日以上排便がない、毎日出ていても排便時の痛みや、肛門が切れるという場合には便秘と言えます。
しかし、排便の回数や状態は年齢変化や個人差も大きく、判断が難しい場合もあります。お迷いの際には気軽にご相談ください。乳幼児期は、離乳食の開始によって食事内容が変化するタイミングやトイレトレーニング時、小学校入学時に発症することが多く、学童期以降は、便意の我慢によって発症することが多いと言われています。
乳幼児期発症の便秘では、適切な治療を早く始めた方が後の経過が良いことが知られています。また、子供の便秘を放置すると腸内の細菌叢に悪影響であることもあり、放置せずに、適切な治療を受けることをおすすめします。
小さいこどもの便秘では、硬い便が肛門を通る際に肛門が切れてしまい、その裂け目の周囲の皮膚が盛り上がって見える見張りいぼと呼ばれるいぼ状の皮膚となることがあります。便秘が改善すると見張りいぼは治るため、便秘のコントロールが重要となります。
出生後早期からみられる便秘や腹部膨満・嘔吐・血便・体重減少などのredflagsと呼ばれる症状が併発している場合には、ヒルシュスプラング病などの病気が隠れている可能性があるので、すぐに受診してください。学童期の便秘については学校のトイレ忌避や生活習慣の乱れなどが原因となっていることがあります。
当院では、良い便を快適に出すことを目標に、本人と保護者の方とともに早寝早起きや朝ご飯の生活習慣や薬物療法などについて一緒に見直していきます。
臍ヘルニア(でべそ)、鼠経ヘルニア
ヘルニアとは、からだの中にある臓器や組織が本来あるべき位置から外に飛び出た状態のことで、こどもによくみられるヘルニアは臍ヘルニア(でべそ)と鼠経ヘルニア(脱腸)です。
鼠経ヘルニア
鼠経ヘルニアは、こどもの1-5%に見られる比較的頻度の高い疾患で、臓器をくるんでいる腹膜が、鼠径部(太ももの付け根あたり)の腹筋の外に飛び出して、膨らんだように見えます。飛び出した臓器には、腸や卵巣が含まれることが多く、外側に飛び出しても、元に戻れば緊急性はありません。しかし、鼠経ヘルニアでは、飛び出した臓器が元に戻らなくなることがあり(陥頓)、注意が必要です。陥頓すると、膨らんだ部分が硬くなり、触ると痛がり、機嫌がとても悪くなります。放置すると、血行が悪くなり、腸など飛び出した臓器の壊死が始まってしまうため、速やかな受診が大切です。鼠経ヘルニアは、陥頓しない場合でも、外科的な治療が必要となるために、専門施設への紹介とさせていただきます。
臍ヘルニア
臍ヘルニアでは、陥頓することは稀であり、主に整容上の問題となります。
赤ちゃんはお母さんのお腹にいるときは、へその緒を通して、栄養を受け取っています。生まれてくると、その通り道は自然とふさがれますが、筋力の未熟さが原因となり、10人に1、2人の割合で、ふさがらないことがあります。泣いたりするなど腹圧がかかると、腸などの一部がふさがりきらなかったへその部分から、ポッコリと出てきます。1-2歳までに9割が自然と治るために経過観察することもありますが、長時間、へその皮膚が伸びた状態となるために、形の良いへそにならないことがあります。このため当院では、臍ヘルニアに対して乳児期早期より、綿球を使った圧迫法を数か月実施しながら経過観察を行います。圧迫法自体は赤ちゃんの負担はなく、侵襲の非常に少ない、簡単な手技の治療法です。ご希望のある方は、お気軽にご相談ください。なお、この圧迫法は生後6か月を過ぎると効果が乏しくなります。生後1-3か月の間の開始が最も効果的です。