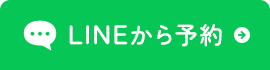お子様のみみ・はな・のどについて
 お子様は大人に比べて、耳・鼻・のどの病気にかかりやすい特徴があります。これらの部位は互いに密接に関係しており、たとえば風邪などで鼻の奥に感染が起こると、そこから耳に細菌やウイルスが広がって中耳炎を引き起こすこともあります。さらに、のどの腫れや痛みが鼻づまりや耳の不快感につながるケースもあるため、どこか一つの不調が全体に波及する可能性があります。
お子様は大人に比べて、耳・鼻・のどの病気にかかりやすい特徴があります。これらの部位は互いに密接に関係しており、たとえば風邪などで鼻の奥に感染が起こると、そこから耳に細菌やウイルスが広がって中耳炎を引き起こすこともあります。さらに、のどの腫れや痛みが鼻づまりや耳の不快感につながるケースもあるため、どこか一つの不調が全体に波及する可能性があります。
小さなお子様はまだ自分の症状を上手に伝えることができないため、耳を頻繁に触る、聞き返しが多い、いびきが強くなる、声がかすれる、鼻が詰まっているといったサインにご注意ください。耳・鼻・のどのトラブルは、繰り返すことで聞こえや発音、睡眠の質に影響し、ひいては学習や運動の発達にも支障をきたす恐れがあります。少しでも異変を感じた場合は早めにご相談いただくことで、悪化を防ぎ、お子様の健やかな成長をサポートできます。
お子様の耳の病気
中耳炎
 こどもの中耳炎は2歳までの乳幼児に多くみられます。こどもは大人と違い、耳管が太く短いために、のどや鼻の炎症が中耳に伝わりやすく、中耳炎となりやすい構造になっています。
こどもの中耳炎は2歳までの乳幼児に多くみられます。こどもは大人と違い、耳管が太く短いために、のどや鼻の炎症が中耳に伝わりやすく、中耳炎となりやすい構造になっています。
夜間に突然「耳が痛い」と大泣きして救急病院を受診したり、朝起きたら耳から黄色い耳だれが出ていたりする。また、保育園に通い始めた途端に風邪をひく回数が増え、その結果、中耳炎を繰り返すお子さんも少なくありません。中耳炎は、こうした小さなお子さんのいるご家庭でよく見られる疾患の一つです。
中耳炎は、発熱や痛み、耳垂れを伴う急性中耳炎と、耳の粘膜の炎症から浸出液が中耳に溜まり耳の聞こえが悪くなる滲出性中耳炎の2つがあります。急性中耳炎を繰り返す、治療をきちんとせずに終えるなどで滲出性中耳炎となることがあります。
急性中耳炎は、症状から発見されやすく、また抗生剤内服治療により1-2週間で治っていきます。しかし、滲出性中耳炎は自覚症状に乏しく、しばしば気づかれずに時間が経ってしまうことがあり注意が必要です。治療は抗生剤や浸出液の排出を促す薬剤を内服しますが、完治には数か月かかることもあります。難治例では鼓膜のチュービングなどが必要となります。
当院では、お子様の耳をみる耳鏡はデジタルマイクロスコープという通常の耳鏡よりも視野が大きく見える機器を取り入れています。場合によっては、耳鏡で見える場面を保護者の方と共有して、経過を観察していきます。また鼻汁の細菌検査を実施して、効果の高い抗生剤を内服していただくようにしています。小さなお子様は鼻汁への対応も大切となるため、ご家庭での鼻汁吸引の説明を行います。
滲出性中耳炎が疑われる場合は、チュービングなどの外科的治療が必要となることがあり、真珠腫性中耳炎の合併がないか画像診断する必要があるため、耳鼻咽喉科の先生をご紹介させていただいております。
先天性鼻涙管閉塞
涙腺で分泌された涙は、目頭から鼻の通り道である鼻涙管を通って鼻に流れ、涙を排出しています。先天的にこの鼻涙管がふさがっている子は、産まれた直後から目に涙が溜まっている、目やにが多いなどの症状が見られます。1歳までに90%以上が自然治癒します。目やにの程度がひどい時には抗菌点眼薬をしていただきます。また目頭マッサージを自宅でおこなっていただき、症状の軽減をはかります。診察時にマッサージのやり方は丁寧に説明します、思い当たる症状がある方は相談してください。
稀に自然治癒が見込めない可能性があるお子さまには、眼科にて外科的な処置が必要となるために専門の施設をご紹介します。
アデノイド
アデノイドは咽頭扁桃のことで、リンパ組織の一つです。4-6歳までに最も大きくなり、10歳頃までに縮小します。このアデノイドが肥大すると鼻閉、鼻汁、口呼吸、いびき、特有の顔貌などを呈することになります。特に鼻腔後方が肥大によりブロックされるため鼻づまりはかなり高度になります。アデノイド肥大は副鼻腔炎や中耳炎の原因ともなり、感染を繰り返す場合や睡眠時の無呼吸を認める場合には摘出手術を検討する必要があります。睡眠時無呼吸の検査等含め、耳鼻咽喉科へ紹介となります。
流行性耳下腺炎
流行性耳下腺炎は、ムンプスウイルスによって発症する感染症で、一般的には「おたふくかぜ」として知られています。この病気は主に耳の下にある唾液腺、特に耳下腺が腫れることで発症がわかります。
子どもが感染すると、顔の片側または両側が大きく膨らみ、発熱や痛みを伴うことがあります。飲食時の嚥下にともなう痛みがあることが多く、食事がとれなくなることがあります。学校保健安全法では「第二種伝染病」に指定されており、医師の診断と登園・登校許可が出るまで集団生活を避ける必要があります。おたふくかぜ自体は命に関わる病気ではありませんが、難聴や髄膜炎、思春期以降の睾丸炎など重篤な合併症を引き起こすことがあります。慎重に経過を見ていくことが大切です。
また飲食時の痛みに対して、鎮痛剤をしっかり内服させ、体力や免疫低下を防ぎます。
お子様のはなの病気
急性鼻炎
 急性鼻炎は、風邪などのウイルスや細菌感染、ダニや花粉などによるアレルギー反応をきっかけとして鼻の粘膜に急性の炎症が生じ、鼻水やくしゃみが出るようになる状態です。発症から数日経過すると、さらさらしていた鼻水が次第に粘り気のあるものへと変化し、鼻の奥にたまっていきます。進行すると喉や気道にまで炎症が広がり、咳、発熱、痰、倦怠感といった全身症状を伴うようになることもあります。
急性鼻炎は、風邪などのウイルスや細菌感染、ダニや花粉などによるアレルギー反応をきっかけとして鼻の粘膜に急性の炎症が生じ、鼻水やくしゃみが出るようになる状態です。発症から数日経過すると、さらさらしていた鼻水が次第に粘り気のあるものへと変化し、鼻の奥にたまっていきます。進行すると喉や気道にまで炎症が広がり、咳、発熱、痰、倦怠感といった全身症状を伴うようになることもあります。
また鼻炎時(花粉症シーズンを含め)には鼻の粘膜が過敏になっていることが多く、ちょっとした刺激でも鼻出血しやすくなります。鼻出血があっても、数分でおさまるようでしたら、大きな心配はいりません。止血しても15-20分以上出血が続く、他にも皮下出血などがある、頻回に鼻出血する、といった場合には、他の原因がある可能性も考えられるため早めに受診しましょう。鼻出血時には、鼻の周囲を冷やし、ティッシュペーパーなどで圧迫して止血しましょう。上を向くと鼻出血がのどに流れ込むため、上を向くのはやめましょう。鼻の入り口などに傷があったり、鼻粘膜がむくんでいることがあるので、受診していただく方が良いでしょう。
しっかり栄養を取り、よく寝ることが一番大切ですが、鼻づまりが長引いて眠れない、食欲が低下するなど見られる場合には、抗炎症薬や去痰薬、解熱鎮痛薬などによる治療を行い症状の軽減を目指します。放置すると中耳炎や副鼻腔炎、さらには気管支炎や肺炎といった重篤な病気に進展する可能性があるため、早めの受診が大切です。
副鼻腔炎(蓄膿症)
副鼻腔炎(蓄膿症)は、顔の中にある副鼻腔という空洞に細菌やウイルス、カビ(真菌)やアレルゲンなどが侵入し、炎症を起こすことで発症します。副鼻腔は額や頬、鼻の奥にある4つの空洞状の構造であり、鼻腔とつながっています。副鼻腔の粘膜から鼻水が分泌されます。
このつながりを通じて感染が広がるため、鼻炎や風邪が長引くと副鼻腔炎を発症することもあります。症状が4週間以内でおさまるものを急性副鼻腔炎、それ以上続くものを慢性副鼻腔炎(蓄膿症)と呼びます。急性副鼻腔炎では、発症時に激しい頭痛を呈することがあり、注意が必要です。
副鼻腔炎の診断には鼻用CTでの画像診断となります。副鼻腔炎が疑われる場合には、CTを完備した耳鼻咽喉科にてしっかり診断することが重要となります。また外科的な治療が必要となることもあり、当院ではお子様の副鼻腔炎が疑われた場合には、お近くの設備が整った耳鼻咽喉科へ紹介し、連携しながら診察をすすめていきます。
先天性耳瘻孔
先天性耳瘻孔は、胎児期に耳が形成される過程で何らかの発育異常が起こり、耳の周辺に小さな孔(あな)が残っている状態を指します。この孔は耳の付け根やその周辺に見られ、見た目だけでは特に問題がないことも多いのですが、内部に膿がたまって炎症を起こすことがあります。
人口の1〜8%程度に見られるもので、決して珍しいものではありません。繰り返し感染を起こす場合には手術での対応が検討されることもあります。
お子様ののどの病気
急性喉頭蓋炎
急性喉頭蓋炎は、インフルエンザ菌などの細菌感染により喉頭蓋が赤く腫れ、気道が狭くなることで引き起こされる疾患です。初期症状は風邪と似ているために区別がつきにくいですが、初期症状として発熱、のどの痛み、くぐもった声、飲み込みにくさなどがあげられます。喉頭蓋は、飲食物が気道に入らないようにふたをする役割を持っており、ここに炎症が生じることで呼吸困難などの深刻な状況を招くことがあります。
軽症であれば外来で点滴治療を行うこともありますが、症状が進行すると気道閉塞による窒息のリスクがあるために入院設備の整った病院へ紹介し、受診していただきます。
この病気は命に関わる可能性があるため、早期の対応が極めて重要です。予防策としては、インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチンの接種が有効とされています。
生後2か月になると接種開始となりますので、早めの接種を心がけましょう。
クループ症候群
クループ症候群は、パラインフルエンザ、RSウイルス、コロナウイルスなどのウイルスや細菌、アレルギー反応によって喉頭が炎症を起こし、独特の咳や呼吸困難を引き起こす疾患です。
特徴的な症状として、夜間に突然、オットセイや犬のようなケンケンした咳が出たり、息を吸い込むときに笛のような音が聞こえることがあります。こうした症状は、喉の炎症によって気道が狭くなることで生じ、時に不安からさらに呼吸が乱れることもあります。
特徴的な咳の症状や嗄声などの症状が現れた場合には、気道の腫れを抑えるために吸入やステロイド内服による治療が必要になるため、速やかに医療機関を受診してください。