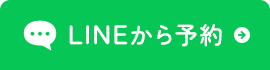一般小児科

当院では、急な発熱や咳、鼻水、腹痛、下痢、嘔吐、発疹などの急性症状をはじめとして、アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、気管支喘息、花粉症といったアレルギー疾患やおねしょ、便秘、頭痛といった慢性疾患まで幅広く対応しております。みみ・はな・のどや皮膚に関する症状についてもお気軽にご相談ください。
またお子様の授乳や食事、発育・発達に関するお悩み、予防接種のスケジュール調整など、子育て全般に関するご相談も小児科専門医が丁寧にお伺いします。
ちょっとした症状でも気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
診察の結果、より専門的な治療が必要と判断される場合には、耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・外科などの専門科や、地域の連携医療機関をご紹介し、速やかに適切な医療を受けていただけるよう支援いたします。
こどもによくある症状
こどもがよくかかる感染症
- インフルエンザ
- RSウイルス感染症
- ヒトメタニューモウイルス感染症
- 突発性発疹
- 新型コロナウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- 手足口病
- ヘルパンギーナ
- 水痘
- おたふく
- アデノウイルス感染症
- 百日咳
- マイコプラズマ感染症
- 尿路感染症
- 伝染性紅斑(リンゴ病)
- ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス性胃腸炎
子供の代表的な急性疾患
発熱
 日本の感染症法では体温が37.5℃以上になると、発熱、38℃以上で高熱と定義されます。平熱が通常よりも高かったり、低かったりする場合には、平熱+1℃を目安にすることもあります。お子様の場合は、体温中枢が未熟なために環境で体温が変化します。このため厚着にしていないか、布団をかけ過ぎていないか確認して少し時間を置いてから再度体温を測ってみてください。またワクチン接種後に発熱することがあり、注意が必要です。特に肺炎球菌ワクチンは10%前後で発熱の副反応があります。ワクチン接種後の発熱の場合、活気や飲みが良好であれば慌てる必要はありません。接種した部位が赤く腫れていないかなど注意してみて下さい。お子様の体調で無理のない時に受診してください。注意が必要なのは、生後3ヶ月未満の新生児、乳児の発熱です。この時期の発熱は、重症感染症などのリスクが高く、小児科での早急な診察が必要です。こどもの発熱のほとんどがウイルスによる感染症によるものです。ミルクの飲みが良く、活気や食欲があれば、慌てずに様子をみて受診しましょう。ただし、けいれんが起きていたり、ぐったりしていたり、水分が取れない、尿が出ないといった場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
日本の感染症法では体温が37.5℃以上になると、発熱、38℃以上で高熱と定義されます。平熱が通常よりも高かったり、低かったりする場合には、平熱+1℃を目安にすることもあります。お子様の場合は、体温中枢が未熟なために環境で体温が変化します。このため厚着にしていないか、布団をかけ過ぎていないか確認して少し時間を置いてから再度体温を測ってみてください。またワクチン接種後に発熱することがあり、注意が必要です。特に肺炎球菌ワクチンは10%前後で発熱の副反応があります。ワクチン接種後の発熱の場合、活気や飲みが良好であれば慌てる必要はありません。接種した部位が赤く腫れていないかなど注意してみて下さい。お子様の体調で無理のない時に受診してください。注意が必要なのは、生後3ヶ月未満の新生児、乳児の発熱です。この時期の発熱は、重症感染症などのリスクが高く、小児科での早急な診察が必要です。こどもの発熱のほとんどがウイルスによる感染症によるものです。ミルクの飲みが良く、活気や食欲があれば、慌てずに様子をみて受診しましょう。ただし、けいれんが起きていたり、ぐったりしていたり、水分が取れない、尿が出ないといった場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
また発熱が続く場合には、尿路感染症、細菌性感染、肺炎や髄膜炎、川崎病などの可能性もあるので、医療機関を受診しましょう。
長引く咳
 お子様が小児科を受診される際、最も多い症状のひとつが「咳」です。多くの場合、ウイルスによる「かぜ症候群」が原因であり、発熱がなく、夜間の睡眠に影響がなく、食欲や元気がある場合には、さほど心配はいりません。
お子様が小児科を受診される際、最も多い症状のひとつが「咳」です。多くの場合、ウイルスによる「かぜ症候群」が原因であり、発熱がなく、夜間の睡眠に影響がなく、食欲や元気がある場合には、さほど心配はいりません。
ただし、咳にはさまざまな種類があります。乾いた咳(ケンケン)や痰がからむ咳(ゲホゲホ)、オットセイの鳴き声のような咳(犬吠様咳嗽)(ケンケン)などがあり、特に後者はクループ症候群や急性喉頭蓋炎といった病気に関連すること速やかな受診が必要です。
気管支喘息の発作による咳の場合にはゼイゼイ、ヒューヒューした咳が、夜間・早朝に特に強く出現します。普段から長期管理薬を服用していても、発作時の治療が追加で必要となることがあるために早めの受診が必要です。
お子様の咳が気管支喘息や喘息様の気道炎症によるものかどうかの判断が難しい場合があります。ゼイゼイした呼吸をする、呼吸がいつもより早い、肩で息をしている、肋骨の下がへこむような呼吸をしている、夜間に何度も咳で目を覚ますといった様子が見られるときには、喘息発作や喘息様気管支炎の可能性もあるため、早めの受診をおすすめします。
医療機関を受診することで、直接、のどや胸の音を確認することができ、また気道の炎症を測定する検査などを受けることができます。気管支喘息や喘息様炎症と診断されると気管支を拡張するためのネブライザーや、吸入器のレンタルが可能なため、症状の軽減が期待されます。
また、非常にまれですが、異物誤飲による咳や胃食道逆流による咳の可能性もあり、これらの疾患が疑われる場合には、専門施設へのご紹介となります。
鼻水・鼻づまり
鼻水は、お子様の体調変化を示すサインのひとつです。
- 透明でサラサラした鼻水は、風邪の初期やアレルギー性の反応
- 白っぽい鼻水は、風邪のピーク
- 黄色〜緑色で粘り気のある鼻水は、風邪が進行しているか、副鼻腔炎などの可能性
上記のような傾向がありますが、鼻水の色や性状だけでは原因を見分けることは困難です。
乳児では、鼻づまりによって母乳やミルクがうまく飲めなかったり、眠れなかったりすることがあります。自分で鼻をかめない年齢のお子様には、ご家庭での鼻吸引を活用することも大切です。クリニックを受診して鼻吸引することも可能です。
子供の場合、慢性的な鼻水・鼻づまりが続くと、睡眠の質の低下や日中の集中力不足、機嫌の悪さといった影響が出たり、長引く鼻水が中耳炎の原因となることがあります。またアレルギー性鼻炎や花粉症が原因なこと、後鼻漏や副鼻腔炎、アデノイドなどの疾患が隠れていることもあり、「ただの鼻水」と軽視せず、必要に応じて医師にご相談ください。
当院では鼻水がかめるようになった年齢のお子様には鼻汁好酸球という、お子様に負担のない検査を実施することで、アレルギーによる鼻水か感染による鼻水かを判断することができます。この鑑別で適切なお薬を選ぶことができるため、症状の軽減が目指せます。
腹痛
お子様の腹痛の原因で最も多いのは、便秘や胃腸炎などの消化器系のトラブルです。ただし、中には虫垂炎(いわゆる盲腸)や膀胱炎や腎炎といった泌尿器疾患、あるいは食物アレルギーが原因となっているケースもあり、注意が必要です。
特に小さなお子様は、体のどこが痛いのかをうまく伝えられず、「おなかが痛い」と表現することがよくあります。腹痛を訴えている場合は、腹部だけでなく全身の様子にも注意して観察することが大切です。
発熱や嘔吐を伴う場合や、冷や汗をかくような持続性の痛みである場合には早めの受診をご相談ください。
ひきつけ(熱性けいれん)について
お子様が発熱した際に突然けいれんを起こすことがあり、これを「熱性けいれん」と呼びます。遺伝的な要因が強く、両親に熱性けいれんの既往があると2-3倍発症頻度が高くなります。多くの場合、生後半年から5歳までの間で、発熱後24時間以内に起こると言われています。けいれんは数分で自然におさまり、後遺症を残すことはありません。しかし、けいれんが5分以上続く、左右どちらか一方の手足だけがけいれんしている(左右対称ではない)、短時間で繰り返すといった場合には、すぐに医療機関を受診してください。
けいれんしている時に、口の中に食べ物や吐しゃ物などがある場合にはすぐに取り除いてください、可能であれば横を向かせます。
しかし、強く抱きしめることや、人工呼吸や心臓マッサージ、舌を噛まないように口腔内に何かを入れることは、窒息やケガにつながるので絶対にしないようにしましょう。
初めて熱性けいれんが起きたときは、どんな様子だったかをよく観察し、来院時にお伝えいただけると診察に役立ちます。動画があると、診察の参考になります。
発熱時にけいれんを繰り返すお子様やけいれんが15分以上続くなどの複雑型熱性けいれんの場合には6歳まで、発熱時にけいれんを予防する座薬を使用することがあります。受診していただき、診察した上で、保護者の方と相談して方針を決定します。
けいれんは突然の出来事で驚かれるかと思いますが、保護者の方が落ち着いて行動されることが大切です。
嘔吐
お子様は、食道や胃などの消化管の配置上、とても吐きやすい傾向にあります。強く咳き込んだときや激しく泣いたあとに吐いてしまうことも珍しくありません。嘔吐のあとに機嫌が良く、食欲や元気があるようであれば、急いで受診する必要はありませんが、引き続き注意して様子を見てあげてください。
食物蛋白誘発胃腸症
特定の食べ物を摂取した1-6時間後に嘔吐を繰り返す場合には、食物蛋白誘発胃腸症と言われる消化管アレルギーの可能性があるため、繰り返す嘔吐のエピソードがあるような場合には受診することをおすすめします。
アセトン血性嘔吐症
8-10歳くらいまでのやせ形の子供に多く見られるアセトン血性嘔吐症も激しい嘔吐が特徴です。自家中毒や周期性嘔吐症とも呼ばれます。乳幼児では傾眠傾向になりやすく、またこの疾患では頭痛、活気の低下、生あくびなどが伴うことが多いです。ストレスや疲労、緊張、感染症などが誘因となり、体内にアセトンと呼ばれる分解物が蓄積することで発症します。誘因となるものをなるべく回避し、脂質を少なめに、炭水化物やたんぱく質の多い食事を心がけるようにしましょう。
嘔吐が出現すると、点滴加療を実施しないと頓挫しないことが多いのも特徴です
また原因に関わらず、発熱や頭痛などの併発する症状がある、嘔吐を繰り返している、飲み物を受けつけない、意識がぼんやりしているといった症状がある場合は、すぐに小児科を受診する必要があります。また1歳以下の乳児の場合、腸が重なり合って閉塞を起こす「腸重積症」の可能性も考えられます。嘔吐に加え、不機嫌や血便といった症状がある場合も、迅速な対応が必要ですので、速やかにご来院ください。
下痢
お子様の下痢は、日常的によく見られる症状のひとつです。元気があり、食事や水分が摂れているようであれば、急いで受診する必要はありません。ただ、体調がすぐれない様子や、尿の量が減っている場合には、脱水の心配があります。
特に乳児は脱水が進みやすいため、「口の中が乾いている」「涙が出ない」「おしっこの色が濃い」といった様子があれば、できるだけ早くご来院ください。
また、おむつをしているお子様は下痢に伴い、肛門周囲がただれてしまうことがあります。この場合には、軟膏塗布が必要となりますので、受診することをおすすめします。
血尿・蛋白尿
血尿や蛋白尿は、尿が赤っぽく見えたり、コーラの様だったり、泡立っていて気が付くこともありますが、保育園や学校の定期的な尿検査で指摘されることが多い症状です。
多くは程度の軽いもので、良性であったり(家族性良性血尿など)、生理的な変化によるものですが、稀に腎臓・泌尿器系の病気や全身的な疾患が原因となるケースもあるため、精査及び定期的な経過観察が必要となります。必ず医師の診察を受けるようにしましょう。
乳幼児の簡易視覚スクリーニング
 当院では、小さなお子様の目の健康を守るために、視覚スクリーニング機器「スポットビジョンスクリーナー」を導入しています。これは、乳幼児期からの目の異常を早期に発見するための画期的なツールです。
当院では、小さなお子様の目の健康を守るために、視覚スクリーニング機器「スポットビジョンスクリーナー」を導入しています。これは、乳幼児期からの目の異常を早期に発見するための画期的なツールです。
視力の発達は確認が難しい
乳幼児は生まれつきはっきりとした視力を持っているわけではありません。視力は成長とともに徐々に発達するものであり、その途中で何らかの異常があっても、子ども自身が「見えていない」と自覚しないことが多く、発見が遅れがちです。
特に3歳未満では、従来の視力検査にうまく対応できないケースが多く、異常の早期発見が難しいという課題がありました。
弱視の早期発見が重要
「弱視」とは、成長期の視力発達が妨げられ、眼鏡をかけても十分な視力が得られない状態を指します。原因としては、強い遠視・近視・乱視、斜視などが挙げられます。
3歳児健診で初めて視力検査を行うお子様が多い中、弱視の兆候を見逃してしまうリスクも少なくありません。この時期を逃すと、その後の視力回復が難しくなることがあるため、早期スクリーニングによる発見と対応が極めて重要です。
生後6ヶ月から受けられる視覚スクリーニング
当院では、生後6ヶ月以降の乳幼児でも検査可能な視覚スクリーニング機器「スポットビジョンスクリーナー」を導入しています。この機器は、遠視・近視・乱視・斜視といった弱視リスクを非接触・無痛で測定できます。
お子様から約1メートル離れた位置から、わずか1秒間、画面を見てもらうだけで検査が完了します。そのため、視力測定が困難な3歳未満のお子様でも安心して検査を受けることが可能です。
弱視リスクの早期発見と適切な治療へ
スクリーニングの結果、異常が疑われた場合には、当院での精密検査・治療につなげていきます。
「弱視」は、視覚の発達過程で異常があった場合に視力が十分に伸びない状態であり、早期に治療を始めることで改善の見込みが大きく変わります。発見が遅れると、将来的に就業制限にかかる職業選択の制限が生じるなどのリスクも考えられます。
そのため、乳幼児期からの早期スクリーニングによるリスク検出と治療介入が、将来の視力と生活の質を守るうえで重要です。