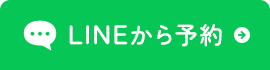食物蛋白誘発胃腸症(消化管アレルギー)
消化管アレルギーって?
 近年、非常に増加している疾患ですが、その病態や機序については十分に分かっていません。多くは新生児期や乳児期に原因食品(粉ミルクや卵黄、大豆など)を摂取することで起こりますが、学童や成人でもみられることがあります。
近年、非常に増加している疾患ですが、その病態や機序については十分に分かっていません。多くは新生児期や乳児期に原因食品(粉ミルクや卵黄、大豆など)を摂取することで起こりますが、学童や成人でもみられることがあります。
症状は嘔吐、下痢、血便といったお腹の症状(消化器症状)が中心で、稀に体重減少や血圧低下などが伴います。
急性型と慢性型に分類され、急性型では、原因食品の摂取から1-6時間経過して症状(おもに嘔吐)が出現するものと、摂取から1日から数週して症状(主に下痢や血便、体重減少など)が出現する慢性に分けられます。
消化管アレルギーの診断
診断には、
①他の疾患ではないこと
②原因と考えられる食品を除去すると症状が消失すること
③原因が考えられる食品を除去して症状が消失した後に、再度摂取を再開すると、再び症状が現れること
で判断します。
臨床の場では特に①の他の疾患ではないことを判断することが重要となるために、場合によっては血液検査やレントゲンなどの実施が必要となることがあります。また①と②で十分に診断できる場合には③の再度摂取させて、症状の再燃をみることは省かれることがあります。
消化管アレルギーの治療
 治療は、通常の食物アレルギーとは違い、10-12か月程度の除去となります。
治療は、通常の食物アレルギーとは違い、10-12か月程度の除去となります。
母乳栄養でないお子さまで、この疾患があるために通常の粉ミルクが摂取できない場合には、高度加水分解乳(ミルフィーやMA-1)や大豆ミルク(ボンラクト)などの代替ミルクを紹介します。
大抵のお子さまは2-3歳で、原因食品の摂取が可能となることが多いですが、6,7歳になるまで症状が継続することもあります。
原因食品の摂取か可能となったかについては、経口負荷試験が実施されます。
この経口負荷試験については、通常の食物アレルギーで行われる負荷検査とは違った準備や方法となりますので、詳しくは診察の時に相談することになります。
一つ、注意が必要なこととして、この食物蛋白誘発胃腸症によって引き起こされた胃腸症には、通常の食物アレルギーの治療に用いられる抗ヒスタミン薬やエピペンといった薬剤は無効となります。
この疾患により嘔吐などの症状が出現した後は、比較的ケロッとしていることも多く、その場合には特に特別な治療は必要ありません。しばらく注意して様子を見ましょう。
繰り返し嘔吐したり、ぐったり感が強い、顔色が悪いなどの症状がある場合は、点滴による輸液、ステロイド薬投与が治療の中心となります。
当院では、診断から症状出現に関するアクションプラン、またその後の治療方針まで丁寧にサポートいたします。
蕁麻疹
蕁麻疹とは
 蕁麻疹(じんましん)は、突然あらわれる赤み(紅斑)やかゆみを伴う皮膚のふくらみ(膨疹)が特徴の疾患です。皮膚の下の真皮の限局性浮腫であり、
蕁麻疹(じんましん)は、突然あらわれる赤み(紅斑)やかゆみを伴う皮膚のふくらみ(膨疹)が特徴の疾患です。皮膚の下の真皮の限局性浮腫であり、
①毛細血管が拡張することで紅斑が
②血管浸透圧が亢進することで浮腫(膨疹)が
③ヒスタミンが刺激されること
で痒みが出現します。
蕁麻疹の原因と症状
蕁麻疹の原因はアレルギー性(特定の食品や薬剤、花粉によるもの)と非アレルギー性(感染や寒冷刺激、疲労、ストレスなどによるもの)があります。非アレルギー性で、原因の特定ができないことも多くあり、特発性蕁麻疹と呼ばれます。
この特発性蕁麻疹とコリン性蕁麻疹と呼ばれる発汗刺激による蕁麻疹が多いと言われています。コリン性蕁麻疹は、入浴や運動、緊張時などで発汗することがきっかけで起こる蕁麻疹で、アトピー性皮膚炎の合併が多く、稀にアナフィラキシーに進展することがあり、注意が必要です。コリン性蕁麻疹で症状が出現したら、冷やしたり、ステロイド外用塗布などで治療し、再び汗をかかないようにすること大切です。
蕁麻疹に特徴的な痒みを伴う膨疹は数時間から24時間以内に消失することがほとんどですが、場所を変えて出現したり、数週間症状が継続し慢性化することがあります。
症状が強い場合や繰り返す蕁麻疹、また半日から1日しても頓挫しない蕁麻疹では早めにご相談ください。
蕁麻疹の治療
 日常生活を見直し、規則正しい生活と十分な睡眠をとることが大切です。原因がはっきりしている場合には原因、悪化因子の回避が重要です。
日常生活を見直し、規則正しい生活と十分な睡眠をとることが大切です。原因がはっきりしている場合には原因、悪化因子の回避が重要です。
原因がはっきりしなくても、蕁麻疹が軽度であれば、冷やして痒みを軽減させるくらいで自然におさまることもあります。しかし、全身に広がる、症状を繰り返す、しっかり治らずに赤みが残ったり、症状が長引く場合には抗ヒスタミン薬の内服が必要となります。
また従来の抗ヒスタミン薬内服だけでは十分な効果が得られない場合はロイコトリエン受容体拮抗薬やH2ブロッカー(ガスター)を併用して治療継続することで治癒を目指します。
蕁麻疹の痒みはかなり強いことが多く本人の負担が大きいため、適切な治療を早めにすることが大切です。