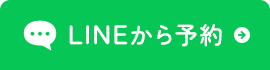インフルエンザワクチンについて

インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスに感染した際に、発熱や全身のだるさなどの症状を軽くする効果があります。特に、免疫力がまだ十分でない小さなお子さまが感染すると、肺炎や脳症などの重い合併症を起こすリスクが高いため、ワクチンによる予防が重要です。
1歳未満のお子さまでは抗体産生がやや低いために、十分な効果が得られるかには議論がありますが、予防効果より重症化の予防を期待して、周囲の大人とともに接種することが大切です。
13歳未満のお子さまは、2回の接種をおすすめしています。
また、インフルエンザウイルスは毎年少しずつ変化するため、ワクチンもその年に流行が予想されるウイルスに合わせて新しく作られています。お子さまの健康を守るためにも、毎年インフルエンザシーズン前の10-11月頃にワクチン接種を受けることが大切です。
当院ではフルミストというインフルエンザの生ワクチンも導入しています。このワクチンは注射での接種ではなく、鼻腔内に噴射することで接種するタイプのワクチンです。インフルエンザの予防効果や重症化の予防効果は、通常のインフルエンザワクチンと同等という報告です。2~18歳の方が対象となっています。注射が非常に苦手なお子さまにはフルミストも検討いただくことが可能です。
重症の鼻炎やコントロール不良の気管支喘息があるお子さまにはフルミストの接種はできないことがあります。
卵アレルギーのお子さまもインフルエンザワクチンの接種は可能です。卵アレルギーのためにインフルエンザワクチンを回避することはありませんので、しっかり接種をしましょう。
当院の予防接種

予防接種は、子どもたちが健康に育つために欠かせない医療の一つです。
こどもたちが、保育園や幼稚園、学校に通うようになると様々なウイルスや細菌に暴露されます。ワクチン接種をしていることで、感染を防いだり、重症化を防ぐことになります。また個人がワクチン接種をすることで、大きな集団感染がおこらないようにすることができます。こうした個人と社会全体の感染拡大防止の観点からも、予防接種は大切です。
私が医師となった20年以上前は、今、乳児に対して行われているB型肝炎やロタワクチン、5種混合ワクチンの中のインフルエンザ桿菌や肺炎球菌が国のワクチン事業として行われていませんでした。大学病院に勤務していると、数か月に1人はインフルエンザ桿菌や肺炎球菌に罹患した乳幼児が髄膜炎や膿胸、脳症といった非常に重篤な感染症を発症し、入院していました。予後も決して良いものではありませんでした。またロタウイルスによる凄まじい嘔吐、下痢で高度の脱水になる子供、またロタによる痙攣をおこし入院となる子供もいました。
国が定期ワクチン(公費で接種できる)事業を拡充してからは、めったにこれらの感染症で入院してくる子供はいなくなりました。当時を知っている者としては、ワクチンの普及がいかに大きな力を持っているかを強く実感します。
確かな論証もなく、ワクチン接種に対する恐怖心や自然感染する方が強くなる、といった考えがネットを中心に多く見られます。小さな乳児は、免疫力が非常に未熟であり、脳関門と呼ばれる中枢系のバリアも脆弱です。インフルエンザ桿菌や肺炎球菌に暴露されたときには、到底太刀打ちできるような力は持ちあわせていないことがほとんどです。これらの情報を見る際には、非常に注意しなければなりません。
大切なわが子だからこそ、ワクチン接種に対して不安や疑問を抱くことがあるのだと思います。私自身、医療従事者であっても、新しいワクチン接種には抵抗を覚えることがあります。しかし、正しい知識や情報をしっかり掴んでいくこと、冷静にメリットとデメリットを天秤にかけて考えることを心がけています。当院では、保護者の気持ちに寄り添った説明を心がけ、納得していただくことを目指しております。押し付けるような対応はせず、落ち着いてご相談いただけるよう努めています。迷っていたり、悩んでいる時には、気軽に受診し、ご相談ください。
ワクチン接種のご予約はお電話またはLINE、Webからお取りいただけます。もしWebでの手続きが難しい場合には、お電話にてお問い合わせください。
※全ての時間帯にて予防接種は可能ですが、14:30~15:30の間は完全にクリーンタイムの時間になりますので感染症などが気になる方はこちらの時間帯にてご予約をお願いいたします。
- ワクチン接種する時に持参するもの
・母子手帳
・予防接種予診票および接種票(定期ワクチン時のみ)
・マイナ保険証と医療証 - 事前に予防接種予診票の記載をしていただいてから受診いただくと待ち時間の短縮につながります。
- 予防接種予診票を紛失した場合には世田谷区のホームページでダウンロードできます。
- ワクチン接種前には必ず診察し、発熱や異常所見を呈している際には接種を見合わせることがあります。また定期予防接種では予防接種予診票が手元にない場合には接種できませんので、ご注意ください。
定期予防接種
国が定める、公費で受けられるワクチンです。定期予防接種は、ロタウイルスや肺炎球菌、B型肝炎、5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ、インフルエンザ桿菌)、BCG、MR(麻しん・風しん混合)、水痘、日本脳炎、2種混合(ジフテリア・破傷風:11歳以上13歳未満で1回)、子宮頸がん(HPV)です。
任意予防接種
自己負担で接種するワクチンです。任意接種に分類されるワクチンには、おたふく風邪、インフルエンザ、A型肝炎、3種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)、ポリオの追加接種、髄膜炎菌ワクチン、Tdapなどがあります。これらは自己負担となりますが、重症化のリスクを防ぐために有効とされており、接種を検討される方は一度医師にご相談いただくことをおすすめします。また任意接種ワクチンの中には自治体が費用を助成してくれるものもあります。自治体で確認してみてください。
生後2ヶ月からの予防接種
日本では、多くの予防接種が国や自治体の支援により無料で受けられる体制が整っており、これはお子さまの健康を守るだけでなく、社会全体で感染症の拡大を防ぐという大きな役割も果たしています。
ワクチン接種は生後2ヶ月を迎える頃から始まります。ただし、ワクチンの多くは複数回の接種が必要であったり、同時接種で実施したり、それぞれの適切な時期に接種することが重要です。
当院では、以下に示す日本小児科学会が推奨しているスケジュールを導入しております。
生後2か月からのワクチン接種スケジュールに不安がある方には丁寧に説明致しますので、ご相談ください。また何らかの理由で規定のワクチン接種が不十分であったり、適切な間隔でなく遅れてしまっている場合にも、母子手帳を確認しながら適切なタイミングをご案内差し上げています。
当院では感染エリアとワクチンエリアを分けており、診察時間内であれば予防接種の受診は可能です。しかし、不安のある場合や、初回のワクチン接種が済んでいない2か月の乳児に対しては予防接種専用の時間帯(クリーンタイム)を設けており、体調不良の患者さんと接触する心配がないよう配慮しております。安心してご来院いただける環境づくりに努めていますので、何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
予防接種のワクチンの種類
予防接種とは、将来かかるおそれのある感染症に対して、あらかじめ免疫(抗体)をつけておくために行う医療行為です。ワクチンを体内に取り入れることで、病原体に対する抗体を作り、実際にウイルスや細菌が侵入したときに速やかに免疫反応が働くように備える仕組みです。
従来のワクチンには、「生ワクチン」「不活化ワクチン」「トキソイドワクチン」の3種類があり、最近ではコロナワクチンに代表される「mRNAワクチン」のような新しいタイプも登場しています。
生ワクチン
生ワクチンは、病原体の毒性を弱めて生きたまま体内に取り入れるワクチンで、自然感染に近いかたちで免疫を獲得するため、少ない接種回数で効果が得られます。日本で使われている生ワクチンには、ロタウイルス、BCG、MR混合(麻疹・風疹)、おたふく風邪、水痘などがあります。
不活化ワクチン
不活化ワクチンは、病原体の毒性を完全に消滅させたうえで、免疫(抗体産生)を得るために必要な成分だけを抽出したものです。抗体を作る力はやや弱いため、複数回の接種が必要になります。代表的なものとしては、B型肝炎、5種混合に含まれるヒブ、百日せき、ポリオ肺炎球菌、日本脳炎、インフルエンザなどが該当します。
トキソイドワクチン
トキソイドは、抗体を作るために必要な性質だけを残して作られるワクチンです。抗体を作る力は生ワクチンと比べて弱めであるため、効果を十分に得るには複数回の接種が必要です。ジフテリアや破傷風のワクチンが該当します。
各種予防接種
小児用肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌は、肺炎や中耳炎の原因となる細菌です。重症化すると、敗血症や細菌性髄膜炎、脳症など、命にかかわる深刻な病気を引き起こすことがあります。
小児用肺炎球菌ワクチンは、生後2か月から接種が可能です。この時期には、肺炎球菌ワクチンに加えて、B型肝炎ワクチン、5種混合、ロタウイルスワクチンなどの予防接種も同時に受けることが推奨されています。複数の感染症から赤ちゃんの健康を守るためにも、早めの接種をおすすめします。
肺炎球菌ワクチンは接種後に発熱を呈することが10%前後に起こります。大抵は1日で解熱します。活気があり、飲みが良いようであれば慌てる必要はありません。お子さまの様子をみて受診してください。
B型肝炎ワクチン
B型肝炎は、ウイルスによって引き起こされる肝臓の病気で、生後2か月頃からワクチンで予防することができます。感染すると慢性肝炎に進行することがあり、将来的に肝硬変や肝がんを引き起こす可能性もあります。
特に乳児期に感染すると、持続感染になりやすく、長期的な健康リスクにつながるため、早期の予防が非常に重要です。
大切なお子さんが健やかに成長するために、B型肝炎ワクチンの接種をおすすめしています。接種スケジュールなどの詳細は、お気軽に当院までご相談ください。
ロタウイルスワクチン
ロタウイルスは、乳幼児に多く見られる胃腸炎の原因ウイルスで、激しい下痢や嘔吐を引き起こします。特に重症化しやすく、脱水症状を起こすことで入院が必要になるケースも少なくありません。またロタウイルスに罹患すると痙攣発作を繰り返すことがあり、非常に重篤となります。
ほとんどのお子さんが5歳までに一度は感染するといわれており、感染力が非常に強いため、保育園や家庭内での流行も起こりやすいのが特徴です。
ロタウイルスには根本的な治療法がないため、予防が何より大切です。ワクチンは飲むタイプの経口生ワクチンで、生後早い時期からの接種が推奨されています。大切なお子さんを守るために、ぜひ早めの接種をご検討ください。
5種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ、インフルエンザ桿菌b型)
5種混合ワクチンは、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、インフルエンザ桿菌b型の5つの感染症を一度に予防できる大切なワクチンです。いずれも重症化すると命にかかわることがあり、後遺症が残ることもあるため、早期の予防が必要です。
特に百日咳やインフルエンザ桿菌は、乳児がかかると重症化しやすく、注意が必要です。そのため、生後2か月を過ぎたら、できるだけ早く接種を開始することが推奨されています。5種類の感染症に対するワクチンが1回のワクチンで実施できるため、お子さまの負担軽減となっております。
BCGワクチン
BCGワクチンは、結核の発症を防ぐためのワクチンです。日本では結核が、現在でも年間約2万人が新たに発症し、そのうち約2,000人が命を落としている感染症です。
特に乳幼児では、結核性髄膜炎や粟粒結核といった重い合併症を引き起こすリスクが高いため、予防が非常に重要です。BCGは、生後5-11か月になる前までに接種することが推奨されています。
高齢の祖父母と同居されている場合などはリスクが上がることが報告されております。お子さんを結核から守るためにも、適切な時期での接種を心がけましょう。
麻しん・風しん(MR)ワクチン
麻しん(はしか)は非常に感染力が強く、高熱や発疹を伴い、重症化すると肺炎や脳炎を引き起こすことがあります。風しんも発熱や発疹を伴う感染症で、特に大人がかかると重症化しやすくなります。
また、妊娠中に風しんに感染すると、胎児に「先天性風しん症候群」を引き起こす可能性があり、耳・目・心臓などに障害が出るリスクがあります。
そのため、お子さんが1歳になったら、すぐにMRワクチン(麻しん・風しん混合)の1回目の接種を受けるようにしましょう。
また5-6歳の就学時前に2回目の定期接種があります。
MRワクチンは2回の接種で9割以上の高い確率で免疫獲得することが報告されています。MRワクチンは必ず2回の接種をするようにしましょう。
水ぼうそう(水痘)ワクチン
水ぼうそうは、水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる感染症です。軽症で済むこともありますが、重症化すると脳炎や肺炎、とびひなどの合併症を引き起こすことがあります。また血液疾患の基礎疾患を有する方にとっては水痘罹患は命を落とす可能性があり、みずぼうそうの流行を作らないことは大切なことです。
お子さんが1歳を迎えたら、できるだけ早めに接種することが推奨されています。なお、水ぼうそうワクチンは1回の接種では十分な効果が得られないため、2回接種することでしっかりとした予防効果が期待できます。
大切なお子さんの健康を守るために、2回の接種を計画的に受けましょう。
子宮頸がん予防のためのHPVワクチン
子宮頸がんの主な原因はヒトパピローマウイルス(HPV)で、特に16型と18型が多く見られます。
HPVは主に性交渉によって感染し、若い女性に多くみられます。日本では女性の約80%が知らずに感染し、自然に治ることも多いですが、一部の感染は持続し、子宮頸がんの原因となります。
年間約10,000~15,000人が子宮頸がんを発症し、そのうち約3,000人が命を落としています。オーストラリアなどのHPVワクチンの接種が進んでいる国では、感染率や前がん状態の発生が大幅に減少していることが報告されています。
またHPVワクチンの接種が進んでいる国では男児への摂取も開始されております。男児へのワクチン接種は成人したあとの咽頭癌のリスクが軽減されることが分かっています。
現在、ワクチン接種に使われるシルバード9は、それまでのサーバリックスやガーダシルに比べて、カバーするHPVウイルスの型が多く、予防効果も80-90%と言われています。
性交渉を経験する前にワクチン接種を始めることが望ましく、標準的には中学3年生までに接種を完了することをおすすめします。2回の接種でも予防効果は同様にありますが、1回目と2回目の間隔を必ず5か月以上あけて、13か月以内に接種することが大切です。
子宮頸がんワクチンは日本に導入された時に副反応の問題が大きくクローズアップされたことで(現在ではこの問題の調査が終了しております)HPVワクチンの勧奨接種が一時期中止されました。1997年4月から2006年4月までであり、これによりワクチン接種の機会を逃した方には、2025年3月まで公費でのキャッチアップ接種が行われていました。現在はキャッチアップ接種に関しては公費での接種はできなくなりました。しかし、お子さまを守る大切なワクチンです、機会を逃したまま未摂取の方はぜひ一度、ご相談ください。
ワクチン接種することによって、若い女性の命を奪う子宮頸がんを予防することができます。大切な未来のために、適切な時期の予防接種をご検討ください。
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
おたふくかぜは、主に子どもに多く見られる感染症で、感染後約2〜3週間で耳の下あたりが腫れ、発熱することが特徴です。
また、まれに難聴や脳炎、無菌性髄膜炎などの合併症を引き起こすことがあります。成人になってから罹患すると精巣炎や卵巣炎の合併症により不妊症の原因となることがあります。
予防のためには、1歳頃と5〜7歳頃の2回にわたりワクチン接種を受けることが推奨されています。大切なお子さまを守るために、ぜひワクチン接種をご検討ください。
自費で受ける予防接種費用
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| B型肝炎 | 6,600円 |
| ロタリックス | 15,000円 |
| ヒブ(インフルエンザ桿菌) | 7,700円 |
| 小児肺炎球菌 | 11,000円 |
| 5種混合 | 17,000円 |
| BCG | 11,000円 |
| MR | 9,900円 |
| 水痘 | 6,600円 |
| 日本脳炎 | 8,800円 |
| HPV | シルガード:25,000円 |
| ガーダシル:16,000円 | |
| 2種混合 | 4,400円 |
| 3種混合 | 5,000円 |
| おたふく | 5,000円 |
※全て税込表記となっています。
血液型検査
| 血液型検査 | 2,500円 |
|---|
※全て税込表記となっています。
文書料金一覧
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 主治医意見書 | 500円 |
| 診断書 | 3,300円 |
| 保険会社関連の診断書 | 4,400円 |
| 英文 診断書 | 5,000円 |
| 治癒証明/登校(登園)許可書 | 無料 (500円) |
| 一時保育用書類 | 3,300円 |
※全て税込表記となっています。